Vol.55 ストレスを“言語化”できる職場のメリットとは?
- 睦美 柴

- 2025年5月25日
- 読了時間: 3分

こんにちは、人的資本健康経営コンサルタントの柴です。
皆さんの職場では、「なんかモヤモヤする」「しんどいけど理由が分からない」といった“言葉にならないストレス”を耳にすることはありませんか?
実はこの“言語化できないストレス”こそが、メンタル不調やプレゼンティーズム(出勤はしているがパフォーマンスが落ちている状態)の大きな要因になっています。
今回は、職場でのストレスを「言葉にする力」に焦点を当て、そのメリットと実践のヒントをお届けします。
1. なぜ“言語化”が重要なのか?
ストレスを感じていても、それをうまく言葉にできないと、適切な対処ができず、心身に負荷が蓄積されていきます。「なんとなくつらい」という感情を抱えながら働き続けることは、集中力の低下や仕事のミス、さらには体調不良につながるリスクも。
実際、厚労省が公表しているメンタルヘルスの調査でも、本人が「体調不良の兆し」に気づいたときには、すでに重度の状態だったというケースが多いのです。
ストレスを言葉にできるようになることで、自分自身の内面を整理しやすくなり、上司や同僚にも「どんなサポートが必要なのか」を伝えやすくなります。これは、健康経営や人的資本経営の基本でもある「対話による早期対応」を可能にする大切な第一歩なのです。
2. 言語化がもたらす職場の変化
社員一人ひとりが、自分のストレスや感情を言語化できるようになると、職場には次のような変化が生まれます。
早期のサポートが可能になる:「体調が悪い」ではなく「最近、業務量が多くて疲れている」と言えれば、上司も具体的に対応がしやすくなります。
職場全体の信頼感が高まる:「自分の気持ちを話していい」と思える環境は、心理的安全性の醸成にもつながります。
チームのパフォーマンスが安定する:ストレスをため込まず、適切に発散・共有できるチームは、生産性も持続的に高い傾向があります。
このように、“言葉にする力”は、個人の健康だけでなく、組織の健全な成長に欠かせないスキルです。
3. 明日からできる!職場での言語化支援の工夫
では、どうすれば社員がストレスを言葉にしやすくなるのでしょうか?大切なのは、「話しても大丈夫」と思える仕組みと雰囲気づくりです。
たとえば、こんな取り組みが効果的です:
週1回の“気分チェックイン”タイムを設ける:「今日はどんな気分?3段階で教えてください」といった簡単な質問から始めてみましょう。
上司自身が感情をオープンにする:「今日はちょっと寝不足なんだ」など、上司が自分の状態を話すことで、部下も自然と口を開きやすくなります。
「言葉の選び方」を学ぶ機会をつくる:メンタルヘルス研修や感情言語化ワークなど、職場での対話スキル向上を目的とした学びの機会を設けるのも効果的です。
“話せる職場”は、聞くだけではなく「引き出せる職場」であることが理想です。そのためには、職場の文化や上司の姿勢がカギになります。
✅まとめ
ストレスの「言語化」は、健康経営を実現するうえでのキーポイント。働きがいやエンゲージメントの向上にも直結する視点です。
WellBridgeでは、感情の言語化やメンタルヘルスを支える社内コミュニケーション設計について、研修や専門職との連携を通じて支援しています。
「うちの職場、もっと話しやすくしたいな」と感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
執筆:WellBridge 柴





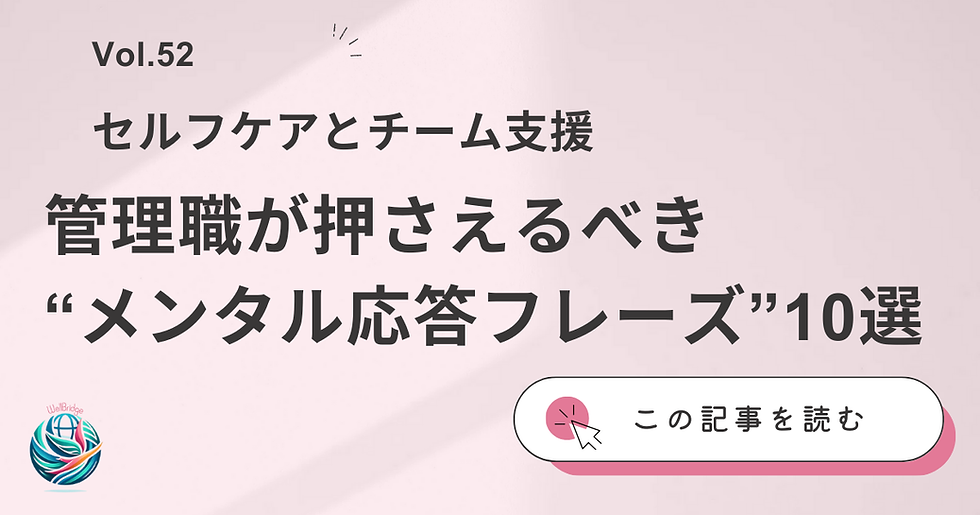
コメント